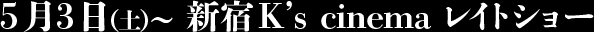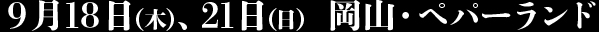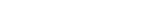
かつて一世を風靡したイングランドのアナーコ・パンク・バンド、CRASS。
“ダイヤルハウス”と呼ばれる家で自給自足の集団生活を送り、自身のレコードレーベル「CRASS RECORDS」を立ち上げ、DIY精神の基礎を確立した彼ら。
妥協のない率直な表現で政治的主張を音楽で表現する彼らはまさに時代の風雲児であり、その人気の一方で痛烈な批判を受けた。しかし、彼らは純粋に自分たちの生活を保ちたかっただけだったのだー。
当時の貴重な映像、彼らの楽曲を織り交ぜつつ、現在もダイヤルハウスで暮らす彼らの様子を映し出したこのドキュメンタリーは、観る者に今日の経済成長のパラダイム、消費中心主義世界への疑問を抱かせる。
彼らは言う。疑問を持ったら主張すべきだ。何故なら、自分を支配できるのは自分だけなのだから、と。
 文/行川和彦(音楽評論家)
文/行川和彦(音楽評論家)
CLASHにインスパイアされて結成したにもかかわらずCLASHをオチョクる曲のオープニングでこの映画がグレイトだと確信した。
まずよくぞまとめたと言いたい。CRASSは究極の政治的なバンドゆえにプロテスト云々の単純な話では収まらないネタの宝庫だからである。でもこの映画は64分にCRASSの肝を凝縮している。何時間も収録したと思しきインタヴューは要所のみをセレクト。黒ずくめになる前で普通の格好が初々しいデビュー・ステージのフィルムをはじめとして当時の映像や写真も適宜挿入されるが、“お宝”も小出しである。もったいないと思うのはぼくだけではないだろう。だがジャンル問わず蛇足のシーンの類を盛り込んで間延びした映画が実に多い。それって監督のエゴで監督のエゴでしかない。バッサリ切ることが引き締まった映画になる決め手であり、それによってドキュメンタリーは主張の強度を高める。
本作はそういうストイックな作りで成功している。アレコレ詰め込みすぎずに焦点を絞ったことでCRASSに馴染みが薄い方も入り込みやすく、と同時にマニアも納得の本質を突く構成にもなっている。センチメンタリズムに流されないCRASSと結論のみを叩きつけるパンクの両方の表現方法を映画作りにも活かし、贅肉を削ぎ落としてCRASSの魅力をダイレクトに伝える。すべてリンクさせながら厳選したテーマの一つ一つに時間を割くことでCRASSの核を際立たせているのだ。
監督と撮影と編集を行なったのはオランダでテレビ・ドキュメンタリーを撮っている男性である。ミーハーなファンや信者みたいな活動家とは一味違うクールな視点でCRASSを捉え、ジャーナリスティックな切り口ならではの簡潔なまとめ方だからこそ彫りの深い作品に仕上がっている。
オーソドックスな音楽ドキュメンタリー映画みたいに“シンパ”のバンドやアーティストや関係者がCRASSを絶賛する声も一切入ってない。そもそも手放しの礼賛で対象を崇めたてる行為こそCRASSが一番嫌うことだ。映画の中のメンバーの言葉を借りれば「思想を共有することに興味はなかった」のだから。
その代わりメンバー自身がたっぷり語る。ただし3人に絞られている。ドラマーでCRASSの歌詞と曲の大半を書いたリーダーのペニー・リンボー。過半数の曲で歌っていたCRASS唯一の男性ヴォーカリストのスティーヴ・イグノラント。ほとんど表には出ないで主にアートワークを担当した女性メンバーのジー・ヴァウチャー。そしてインタヴューはなく映るのもわずかな時間だが、CRASSの女性ヴォーカリストの一人であるイヴ・リバティーンのお茶目な姿も拝める。
この映画で扱ったトピックをいくつか挙げておく。
むろんCRASSが始まったいきさつの話は落とさないが、ダイヤルハウスの成り立ちとコンセプトにも時間を割いている。緑に囲まれて農作業も十分できる広大な土地を有して部屋がいくつもある建物に住み、自給自足で生活が成り立つことも理解できる視覚アピール十分の映像だ。厨房に立つ姿などもカメラがとらえ、“石頭”のイメージをくつがえすペニーの暮らしぶりも楽しめる。
70年代前半に起きた米国の政治スキャンダルのウォーターゲート事件をもじった名称の“サッチャーゲート・テープ”の真相を、生の音声込みで露わにしたシーンも興味深い。英国と南米アルゼンチンとの間で勃発した82年のフォークランド紛争(≒戦争)にまつわるネタで、当時の英国首相マーガレット・サッチャーと米国大統領ロナルド・レーガンの声をコラージュし、電話の会話を“捏造”したテープを英米などの大新聞社に送り付けて波紋を呼んだCRASSならではの強烈な“イタズラ”だ。
いわゆるグラフィティ戦術をはじめとしてゲリラ的でありながら分別を持って事を進めたことを話す一方、CRASSの活動中最も過激な直接行動で他のアナーキストと共に金融街を攻めた活動末期の“ストップ・ザ・シティ”の真相も、リーダーが明かす。
適度に曲が挿入される際にレコードのインナースリーヴと同じくタイプライター書体で歌詞がスクリーンに書き殴られるのも、インパクト大だ。言葉数が多く大半の曲は速射されて映像に追いつけないから“部分訳”になるが、もちろん日本語字幕付だから、この声でこの言葉!というのがリアルタイムで感じられる映画ならではの醍醐味が堪能できる。
かつてヒッピーが唱えた“ラヴ&ピース”ならぬ“アナーキー&ピース”をスローガンにしていたバンドだし、“anarchy”の“A”を“○”で囲んだ有名なマークが象徴するようにCRASSといえばアナーキー!というイメージが強いにもかかわらず、そのへんについてのツッコミは入れてない。言葉でアナーキーを語るとアカデミックになりがちだし、そもそもCRASSは論理的にアナーキーを突き詰めたわけでもない。でもCRASSが思い描いたアナーキーの姿はこの映画の中で今もしっかりと進行している。
2006年の映画だから撮りおろし映像も厳密に言えば8年前のものだが、CRASSを“現在進行形”の視点で描いているのも高ポイントだ。感慨にふけるシーンを多少含むとはいえ“昔は良かった……”とノスタルジーに浸る映画とは完全に一線を画している。その一つがダイヤルハウスに集まってきている人たちとの交流シーンだ。CRASSのオーガニックなライフスタイルに近い現代の“パーマカルチャー(人間だけでなく自然を尊重するエコシステムに基づく生活文化)”も、CRASSに絡めて大きくフィーチャーしている。
自然回帰の生活様式や平和の取り組み方などでCRASSが“時代遅れのヒッピー”とも呼ばれていたことに対して、ジーは「ヒッピーには夢があったわ。もちろん私たちにもね。私たちの夢は人々をひとつにすることだった」と言っている。その発言箇所で“Come Together”というフレーズを含めているのはBEATLESの曲名を意識してのことに思える。
映画の中では言及されてないが、リーダーのペニーはジョン・レノンへのシンパシーを隠さない。レノンもラヴ&ピースを活動のキーワードにしていてヒッピーの意識に通じていたが、70年代のパンクの多くは“Never trust a hippy”の価値観であり、その流れをくんでニヒリズムを強めた80年代初頭の荒くれパンク・バンドには、CRASSがヒッピー崩れのインテリに映った。
半分事実ではある。上流中産階級で生まれ育ったヒッピーの生き残りで結成当時三十代半ばのバンド最年長のCRASSの司令塔ペニーがそうである。だが労働者階級で結成当時十代終盤のバンド最年少のスティーヴもCRASS創設メンバーで、一つのパンク・バンドの中で同じ釜の飯を食うことはなかなかありえない立場の二人が核だった。15歳近く歳が離れ、英国では厳然として根を張る階級が違う二人のコントラストが最大の見どころだ。
CRASSの両輪のペニーとスティーヴがこの映画の中で交わるシーンはない。二人共ボディはさすがメタボとは無縁でシェイプアップされているが、CRASSの後の暮らしぶりの明らかな違いが映し出される。ジー・ヴァウチャーと共に昔と変わらずダイヤルハウスでの暮らしを続け、“煙”をふかして庭いじりをしながら世間と隔絶した生活を送る、ボサボサの白髪の長髪で浮世離れした頑固ジジイのアーティスト肌のペニー。ガールフレンドと思しき女性と家からパブに赴いてビールを飲みながら周りの酔客と共にテレビでサッカー観戦を楽しみ、丸めた頭で気のいいオッサン風だからこそ中年ストリート・パンクスそのものの庶民肌のスティーヴ。よくぞCRASSの本質の両極端を端的に捉えた!とうならされる。
恵まれた環境で育った人間の理想論と子供の頃から生活に追われた人間の現実論の軋轢こそが、CRASSのカオスの源でありエナジーだったことがこの映画にも刻まれている。タブーにされがちな経済的な現実や“お金”に対する考え方が醸し出されている点も特筆したい。本音を漏らした直後に「今の発言は撤回する」と言うシーンまで削除せずに収めたところにも、監督の本気の取り組みとメンバーの“検閲ファック・オフ!”の姿勢が表われている。
話題を厳選しているとはいえ、ジョージ・バーガー著の労作本『CRASS』では言及されてないネタにもけっこう触れている。英国では切っても切れないサッカーのネタを絡め、TシャツがつなぐCRASSとベッカムの関係に焦点を当てて葛藤を炙り出すシーンも面白い。
アートワークに表われていたCRASSお得意の“スカトロ・ネタ”をさりげなく挿入しているところには笑わされる。リーダーのペニー自ら“ソレ”を実践しようと試みるシーンをしっかり収めているのだ。シリアスに留まらないCRASS直伝の“センス・オブ・ユーモア”のダシも効かせているからこそ、この映画はリアルな仕上がりになっている。
映画のタイトルは84年のCRASSのラスト・アルバム『Yes Sir, I Will』の最後に出てくるフレーズで、ライヴ中のステージ後方の垂れ幕にも記された言葉だ。そんな“遺書”と共にCRASS終焉の弁が語られる。
ドキュメンタリー映画は言葉の比重も高くなりがちだし本作も例に漏れないが、理屈じゃなくスクリーンで見る必然性たっぷりの映像力で魅せるところが何より重要である。さりげなく侘び寂びの効いたイングランドの空気感が伝わってくるのだ。CRASSが生まれた地の温度が肌で感じられるし、雑草の緑と室内の調度品の匂いが漂ってくる映像からは情趣も滲む。挿入されるCRASSの曲はどれも扇情的だが、映画全体は静謐と言ってもいいほどの佇まい。だからこそ深々とはらわたに響く作品になったのである。
文/行川和彦(音楽評論家)

CRASSのスタートはロンドン・パンクのムーヴメントがピークを迎えた77年のことだが、農業を営める広大な土地付きの住居をリーダーのペニー・リンボーがロンドン郊外のエセックス州で見つけた67年まで、起源はさかのぼる。
ダイヤルハウスと呼ばれるその家は出入り自由で、文学や絵画などの芸術をはじめとする表現活動を志す人たちが訪れていたが、その一人のスティーヴ・イグノラントがCLASHのライヴに刺激を受けてパンク・バンドの結成をペニーに持ちかけて結成される。ペニーのドラムとスティーヴのヴォーカルだけでデモを数曲録音した後に他のメンバーが次々と参入。ヴォーカル、2本のギター、ベース、ドラムの5人でのプレイを基本にしつつ曲によって多少ヴォーカルが入れ替わり、強烈なコラージュ・ジャケットのアートワーク担当のメンバーも含む男性5人と女性3人の実質8人編成で活動した。CRASSのアティテュードを象徴するように一般的なバンド形態に囚われず自由な体制をキープし、大所帯にもかかわらず7年間メンバー・チェンジ無しだったことも求心力の強さを物語る。
初期の代表曲「Punk Is Dead」の歌詞にも表しているように、商業主義に絡め取られたSEX PISTOLSやCLASHなどの初期パンク・バンドを反面教師にし、徹底したリアルDIYの道を貫く。リリース元のクラス・レコードのレーベル運営も、レコーディングも、アートワークも、プロモーションやライヴの手配も、すべて自分たち自身で行なうという、パンクの基本のDIYアティテュードを突き詰めた。
そもそもCRASSの根城のダイヤルハウスにおける日常生活自体が自給自足だった。
CRASSは過去のどのバンドよりも政治的な展開をした。78年10月録音の18曲入りのデビュー盤『The Feeding Of the 5000』のジャケットにも書かれたフレーズの“アナーキー&ピース”の理念に基づく、平和主義を基本に活動。誰にも支配されず独立した一人一人の行動が平和につながるということだ。反戦、反核、反キリスト教、反物質主義、反動物虐待、反性差別、反環境破壊などの思いを表していた。要はあらゆる既成の価値観を疑え!といったことだが、既成の多くのパンクに宿るニヒリズムにも否定的だった。“fuck”を多用した挑発的な歌詞だけでなく、単なるデモの類に留まらない直接行動もCRASSが先駆けた重要な表現で、過激なactivist(≒活動家)とは一線を画して思慮深く非暴力を貫いたことも忘れてはならない。
もちろんCRASSの曲はパンク・ロックと言えるが、伝統的なロックンロールのフォーマットから解き放たれていた。ペニーのビートは“マーチング・ドラム”のリズムを多用し、2本のギターはファズが猛烈に効いたモノトーンの音で、既成のパンク・スタイルを大きく逸脱。ノイズやコラージュもミックスしていたが、頭デッカチには陥らずに飛び跳ねてダンスできる扇情的なサウンドがCRASSの身上だった。5枚のオリジナル・アルバムはもちろんのこと、10枚近く出したシングルも一枚一枚が独立した一つの作品であった。CRASSのモチーフは国内の問題が多く英国から普遍的に世界を見ていく手法だったが、日本語のナレーションから始まり日本の伝統音楽もブレンドした81年の衝撃のシングル「Nagasaki Nightmare」では、広島の陰に隠れがちな長崎に焦点を当てていた。
インタヴューによって発言が異なるとはいえCRASSは、ジョージ・オーウェルの小説のタイトルを意識したと思しき“1984年”に向かってカウントダウンしていく活動をしていたが、メンバー間の不和と長年の闘争による疲弊が重なって結果的に84年に終焉を迎えた。
CRASSが他のたくさんのバンドとアーティストの作品を自分たちのレーベルから出したことも付け加えておく。ビョークがヴォーカルだったK.U.K.L.も2枚のアルバムをリリースしており、ポピュラーな音楽を世界に放ちつつステージ上でチベットやコソボの問題に触れるなど世界を騒がす彼女に代表されるように、CRASSの影響は無限に広がっている。

アレクサンダー・エイ
1960年、オランダ・アムステルダム生まれ。オランダのテレビネットワークVPROやNPSのテレビドキュメンタリーを中心に、これまでに数多くの作品を手がけている。
作品歴として、山形国際ドキュメンタリー映画祭にも招聘された、元テロリストのハンス・ヨアヒム・クラインが半生を振り返る『あるドイツ人テロリストの告白』(2005)、『Euro-Islam According to Tariq Ramadan』(2005)『Bijlmer, the Rough Guide』(2003)、など。

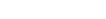
日本において多くの人々が私の作品にインスパイアされているという事を知り大変光栄に思います。
しかしCRASSの為に手掛けた絵画やコラージュの原画を日本で目にした事がある人はほとんどいません。
いつの日かそれらを披露することが出来るかもしれません。
現在の私の作風はCRASSの頃からはかなり変わっており、30年以上前のCRASS作品から私を解き放ち、
現在の私を寛大に受け止めてくれる事を願っております。
と同時に、人々が己を表現し、如何なる形であれそれが次の世代へと力と助けになることを願っております。
Love gee
ジー・ヴァウチャー(CRASS・アートワーク)
翻訳/スタンリー・ジョージ・ボッドマン(TURTLE ISLAND/STORM OF VOID)
てめえのケツはてめえで拭け!のアナーキー&ピース・ドキュメンタリー。
ジョン・レノン好きもビョーク好きもCARCASS好きもCATHEDRAL好きも
アンチCRASSもみんな見るべし。
行川和彦(音楽評論家)
前衛美術家、アナキスト、ヒッピー、失業者…背景も様々な逸脱者たちの共同体から生まれた
パンクバンドCRASSの「黒い」ラブ・ストーリー。
成田圭祐(IRREGULAR RHYTHM ASYLUM)
<不自由になる方法>が布教されるこの世の中で、<自由になる道>はたった一つしかない!!!!!!!
それはDIYを真っ当することだ!!!!!!! CRASSの教義にはその全てがある!!!!!!!!!!!
Anarchy & W.Peace!!!!!!!!
宇川直宏(DOMMUNE)
神格化する必要は無い。
"自分を支配できるのは、自分だけ"
自分自身の生き方を考える、なんて素晴らしいことだろう!
TAYLOW (the原爆オナニーズ)